404 Not Found
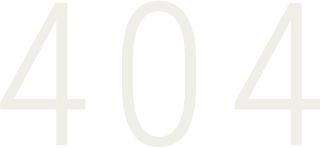
お探しのページが
見つかりませんでした
申し訳ありません。お探しのページは
すでに削除されている・公開期間が終わっている
・アクセスしたアドレスが異なっている
などの理由で見つかりませんでした。
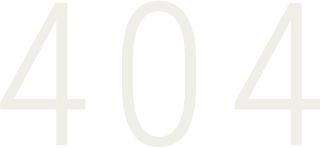
申し訳ありません。お探しのページは
すでに削除されている・公開期間が終わっている
・アクセスしたアドレスが異なっている
などの理由で見つかりませんでした。